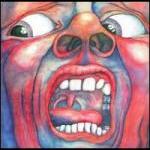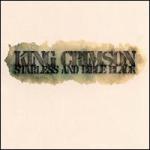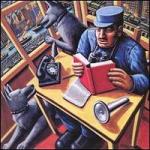|
1969年にデビューアルバム「In The Court of Crimson King」で、ビートルズのラストアルバム
「アビー・ロード」を英国チャートTOPの座から蹴落として一気に時代の寵児となったKing Crimson。
彼らの音楽は、当時の既成のRockの概念を打ち破ったようなインパクトがあり、独特の世界観を持っ
ている。それはリーダーであるロバート フリップ(G)の強力なリーダーシップに因るところが大きい
が、同時にそれがメンバーにとって煩わしいことでもあったようで、脱退やら何やらでメンバーチェ
ンジが絶えることがなく、いわゆる70年代クリムゾンのアルバムで1枚とて同じメンバーでレコーディ
ングされたアルバムがなかった。 1974年にアルバム「Red」を最後に突然の解散宣言により、70年代クリムゾンの幕は降ろされるが、 1980年代に入り突然の復活をし、3枚のアルバムを出して再び眠りに着いた。このとき復活したクリ ムゾンはバンド名こそ「King Crimson」を名乗っていたが、70年代クリムゾンとは全く違うといっても いいほど音楽性が変わっており、ファンの間ではこの復活したクリムゾンに対して賛否両論が渦巻いた。 1990年代に入り再び現れ、名盤「Red」を彷彿させるようなメタリックなクリムゾンとして復活し、 ダブルトリオ編成という特殊な形態によってダイナミズムを表現。現在でもその延長上としての発展 的な活動を続けている。 時代ごとに突然現れては、目的を果たすと眠りに着く。既存のミュージックシーンには目もくれず、 自分たちの求める音楽をひたすら追求する修行僧の如き音楽集団。king Crimsonとはそんな音楽共同体 なのではないかと思う。 |
| In The Court of Crimson King(1969) | ||||
|
King Crimsonのデビューアルバムで、ビートルズのラストアルバム「アビー・ロ
ード」を蹴落として全英のアルバムチャート1位を記録した衝撃のアルバム。ジ
ャケットデザインも衝撃的だが中身も衝撃的で、私がプログレにハマるきっかけ
となったアルバムでした。
私の音楽遍歴は、小学生の低学年で兄の聞いていたビートルズを好きになったの が最初で、その後中学になるとフュージョン(ザ・スクウェアーやカシオペアなど) やオフコースなどにハマリ、高校になるとバンドブームにも影響されて今度は一気 にRock野郎と化し、大学に入りたての頃はアメリカンハードロックやヘヴィメタルにすっかり染ま っていました。そんな遍歴の過程でどのジャンルにも何か物足りなさを感じていま した。そこへこの異様なデザインのアルバムを目にしたとき、「何なんだ、このイ ンパクトの強いジャケットは!」「キングクリムゾン? 聞いた事ねぇバンドだな。コイツ らいったい何なんだ?」という感じでその場でかなり驚いていました。 怖いもの見たさとはよく言いますね・・・つい買っちゃいました。この1枚を「つ い買っちゃった」ことで、後々までプログレにハマってしまうなんてこの時は、全 く思いもしませんでした。このアルバムを聴いて、それまで感じていた「物足りな さ」とは何かがハッキリしたんです。私の感じていた物足りなさとは、誤解を恐れ ずに言わせていただくと、それまで聴いてきたどんな曲も「曲の構成がワンパター ン」という部分でした。ところがこのプログレなるジャンルはどうでしょう。1曲 の中で展開がめまぐるしく変化したり、イントロからは想像がつかないような曲の 終わり方をしていたりと、一言で言うと「ドラマティック」なのです。「俺の求め ていた音楽っていうのはコレなんだ!!」と、まさに「ビビッ」と来ました(笑)。 さて、このアルバムの中身についてなんですが、言葉ではうまく言い表せません。 1曲目の「21st Century Schizoid Man」は日本語タイトルでは「21世紀の精神異 常者」となっていて、曲を聴いてみるとそのタイトル通り「異常者」的なサウンドに なっています。ヘヴィメタルのような「破壊的」な感じではなく、「暴力的」な緊張感の ある曲です。キング クリムゾンの曲で恐らく一番知られている曲ではないかと思われます。 つい3~4年前には某自動車会社のCMのタイアップとして使用されていたりもしまし た(何十年か前にもCMにタイアップされていたという話も聞いた事があります)。キング クリムゾンを全く知らない人でも、イントロを聞けば「聞いたことある!」っていう人 も多いかと思います。3曲目の「EPITAPH」なんかは、メロディそのものだけでも何 か絶望的な感じがするのに、歌詞の内容を見るともっと救いようのない虚脱感に襲わ れてきます。4曲目の「Moon Child」は、曲の途中から即興的なセッションとなって いて、緊張感のある構成となっていて、最後の「The Court of Crimson King」は、 「幻惑的」な雰囲気の不思議な曲になっていて、アルバム1枚の中に「喜怒哀楽が散 りばめられている」といった印象です。 私にとってこのアルバムは、かなり惹きつけられる魅力を持った1枚と感じています が、人によって好き嫌いがハッキリ分かれことは間違いないと思います。ただ、1969 年に発表されたこのアルバムの持つインパクトやエナジーは、30数年経った現在で も全く色褪せていないことは確かです。リーダーであるロバート フリップも「キングクリムゾンの 名盤」の1つとして認めているこの1枚。人生経験のひとつとして一度聴いてみませ んか?もしかしたら、あなたの音楽概念が変わるかも知れません。 |
|||
| In The Wake of Poseidon(1970) | ||||
|
1st Album「In The Court of Crimson King」で衝撃的なデビューをしたキング クリムゾンの2nd Album。
1st Albumの姉妹作的なアルバムとして製作したという話を聞いた事があります。なので、全体的な
構成は1stとほぼ同じ感じです。聞き比べてみると分かると思いますが、1stと似たような感じの曲
のオンパレードです。「聴き易さ」という点で言うと、こちらの方が格段に聴き易いと感じます。
さすがは姉妹アルバム!!といったところでしょう。2曲目の「Pictures of a City」は1stの「21st Century Schizoid Man」を連想させるし、3曲目の「Cadence and Cascade」は「I Talk to Wind」 を、4曲目の「In The Wake of Poseidon」は「EPITAPH」をそれぞれ連想させる曲になっています。 私が特に気に入っているのは7曲目の「The Devil's Triangle」で、最初から最後まで全編が物凄い 緊張感を持った11分を超える大作です。ただ、気に入っているからといっても、よく聴いているとい うわけでもありません。何しろ最初から最後まで緊張感のある曲なんですから………気疲れするん です(笑)。 1stと同じような曲構成でありながら、1stよりも耳に馴染みやすいものが多いこのアルバム。ともす れば、1stの強烈なインパクトの後を受けて無難に仕上げた2作目だとも思われかねないアルバムにも 感じられますが、「名作」ではないにしても「秀作」であると、私はそう思っています。 |
|||
| Islands(1971) | ||||
|
デビューの頃と比べると、もう随分とメンバーの顔ぶれが変わってしまった。それもそのはず、
リーダーのロバート フリップ以外オリジナルのメンバーがいないのである。ラインナップは、
ロバート フリップ(G)、ボズ バレル(Vo,B)、メル コリンズ(Flute,Sax,Vo)、イアン ウォーレ
ス(Dr)という布陣で臨んだ5th Album。
このアルバムはKing Crimsonの中にあってもかなり特異な感じのあるものだと思う。その訳は、 それまでのような「幻惑的」「叙情的」だと言われていた「クラッシックのような形式主義」 的スタイルから、ベースラインとなる曲に即興による肉付けをしていくようなジャズ的なスタ イルへと変化していったからで、それまでのアルバムとはガラッと趣が変わっています。この 傾向は、後のKing Crimsonのスタイルを決定付けるものとなるんですが、このアルバムはその 過渡期として位置づけられるようなものだと思います。 私個人的には、何か中途半端な感じのする印象で、それほど好きだというわけではありません。 それは先に書いたように、スタイルが変わる過渡期的なものだったので中途半端なイメージな のも仕方がないと思います。もしこのラインナップで何作か出していれば、もっと明確にスタ イルが固まったと思うので、その点ではもう少しこのラインナップでアルバムを出してみて欲 しかったと思いました。……そう、このアルバムリリース後の全米ツアー終了後にロバートを 1人残してメンバー3人が脱退してしまったのです。本当にメンバーの出入りの激しいバンド だ(笑)。 このアルバムからのお気に入りといたら「Prelude: Song of the Gulls」「Islands」です。 「Prelude: Song of the Gulls」は室内楽的な心地よい曲でプレリュードという名にふさわし く、その後に続く「Islands」へ誘うようなナンバーとなっています。そして「Islands」は、 King Crimsonの作り上げてきた「絶望的」な「虚脱感」といった世界観とはうって変わって、 「愛」を肯定したKing Crimsonには珍しいラヴソングになっています。この曲は本当に感動的 なバラードとなっています。この曲を聴くためだけでもこのアルバムを買う価値はあると思い ますよ。 |
|||
| Larks' Tongues in Aspic(1973) | ||||
|
King Crimsonフリークの間では、アルバムごとにメンバーチェンジがあるのでそれぞれ
「第1期」「第2期」……などとラインナップの区分があるようですが、その区分でい
いうと「第5期」に当たるラインナップで発表した6th Album。メンバーは、ロバート
フリップ(G)、ジョン ウェットン(Vo,B)、ビル ブラッフォード(Dr)、デヴィッド クロ
ス(Violin)、ジェイミー ミューア(Precussion) 。スタイルも過去のKing Crimsonのス
タイルとは決別したような斬新なものとなっていて、前作「Island」のスタイルをより
明確にしたアルバムとなっています。
私個人的には、この「第5期」と呼ばれるKing Crimsonが一番好きなんです。何と言って 表現すればいいのでしょうか。ダイナミックでありながら繊細さも持ち合わせているよ うな爆発的なエナジーを感じるのです。それが如実に表現されている曲が「Larks' Ton gues in Aspic,Part1」だと私は感じます。ボリュームを余程上げないと聞こえないよう なイントロから始まりますが、このイントロも緊張感を煽るようなメロディラインになっ ていて、そこから一気にアフリカンビート的な強烈なリズムを爆発させてきます。そして 曲の後半にもデヴィッド クロスの繊細にして緊張感のあるバイオリンをはさんでエンデ ィングへとなだれ込む。この曲を聴くといつも体が熱くなってきます。また、「The Tal king Drum」から「Larks' Tongues in Aspic,Part2」の一連の流れは興奮せずにはいられ ません。 その他の曲も以前のような叙情性とは一味違ったものがあり、何よりもジョン ウェットン のヴォーカルがとてもマッチしていて、これほど一体感のあるKing Crimsonは無いと思い ます。第5期のスタートに当たって「より即興的な面を打ち出した音楽を…」というのが コンセプトになっており、アレンジ60% / 残る40%が各メンバーの自由な発想の下での アドリブによるものでありながら、前作の各パートが自己主張して一人歩きしたような 散漫なものとは違い、とてもグルーヴ感に溢れています。 このアルバムには、一触即発するような危険な香りとつけいるスキの無い強固なグルーヴ 感、そんなものを感じます。私にとってのKing Crimsonの名盤の1つです。 |
|||
| Starless and Bible Black(1974) | ||||
|
前作で新しいKing Crimsonのスタイルを確固として打ち出し、それに続く7th Album。
残念ながら、パーカッションのジェイミー ミューアがKing Crimsonから離れてしまい、
またもラインナップが変わってしまった。前作では強固なまでのグルーヴ感を見せつけ
史上最強と思われたラインナップが早速崩れてしまった。どうしてこうも出入りの激し
いバンドなんだろう(笑)。(いやいや笑い事ではない)
さて、このアルバムはスゴイです。なにが凄いかって、「The Great Deceiver」「Lament」 「The Night Watch」の3曲を除いて全てライブ音源によるものだからです。「The Night Watch」にしてもイントロ部分に関してはライブ音源のものであり、ライブ音源の曲にし ても全てインプロヴィゼーション(即興)による曲であるからです。そのライブ音源とは 後で紹介する「The Nightwatch(Live at Amsterdam Concertgebouw)」 からのもので、そちらを聴いてもらえれば間違いないと分かるはずです。 凄いアルバムなんですが、「解りにくい」といったところが最初の印象です。正直最初 聴いたときは何をやっているのかよく分からない感じで、ハッキリ言って飽きました。 前作のような激しいグルーヴ感がだいぶ影が薄れ、ひたすら緊張感のある即興セッション ばかりが目立ち、聞き手のこちらとしては理解に苦しみます。ですが、聴き込むうちに 段々とその世界に引き込まれるようになりました。アルバムに付いてるライナーノーツ の表現を借りるとこういうことです。 『たとえば、男が一人、なんの特徴もない木の椅子にぽつんと掛けているとする。男は 無言である。いや無言であるばかりか、動こうともしない。身じろぎもせず、彼はただ じっと座り続けている。 一般的にはこれほど退屈な場面もないだろう。だが、この何の変哲もない、退屈の見本 のような情景に、どうしても惹きつけられ、いつまでも見飽きないというような場面は あり得ないものだろうか。 死刑囚の不動の沈黙がなぜこれほど我々の心を捉えるのか。"死"という決定的瞬間をめ ぐる実話的興味にひかれていることもたしかである。だが、それだけではないはずだ。 刑の執行を待ち受けている囚人の全神経は刻々と迫ってくる最後の時間に向かって、 極度の集中を続けている。彼がもはや泣き喚いたり騒ぎたてたりしないしないのは死の 恐怖を克服したためなのか、そんなことは分からない。ただ、おそらくその沈黙の凄さ にすべてが賭けられているといっていいのだ。彼には心臓の鼓動も自分の呼吸音も異様に 大きく感じられているに違いない。全身のエネルギーは、あるもののために、完全に 使い果たされてしまっている。 ただ静かに椅子にぽつんと座っている男の姿は、全身の筋肉を躍動させ一時も休むこと のないスポーツ選手の激烈な動きよりも、数百倍多くの出来事を語っているのである。 (アルバム「Starless and Bible Black」 広瀬陽一氏によるライナーノーツより一部引用) つまりそういうことなのです。この広瀬氏によるライナーノーツは私にはとても的確に 表現されているように感じられました。そうなんです、一見つまらないように聞こえて しまうこのアルバムですが、聴けば聴くほど目を背けることのできない圧倒的な存在感 を思い知らされる1枚なのです。ストイックなまでに研ぎ澄まされた感性のぶつかり合い、 そんな緊張感を漂わせているアルバムです。 |
|||
| Red(1974) | ||||
|
70年代のKing Crimsonのラストを飾る8th Album。ここでもまたメンバーが去ってしまった。
前作「Starless and Bible Black」製作後のツアーが終了した時点でデヴィッド クロス(Violin)
が脱退し。、ロバート フリップによると「彼はとても感受性が強くロックビジネスをや
っていくには紳士的過ぎた」ということや、ツアーの連続で体調も悪化していたそうである。
従って、ラインナップは残った3人(フリップ、ブラッフォード、ウェットン)となった。
しかし、ゲストミュージシャンとしてかつてのメンバーであった、メル コリンズ、イアン
マクドナルド、そして体調を持ち直したデヴィッド クロスなど懐かしい顔ぶれが参加した。
また、レコーディングの前から、イアンがクリムゾンに復帰するのではないかという噂が流
れており、ロバート フリップも今後はイアンを入れてカルテットでやりたいという話もして
いたそうだが、そんな話もどこへやら、その何日後かには突然の解散宣言で70年代クリムゾン
の歴史にも終止符を打つことになる。 その後80年代に再び復活するが、こちらのクリムゾンは私にとってもはや「別モノ」であり、 ファンの間でも賛否両論であったそうだ。(この復活に当たっては、ロバート フリップ自身 昔のクリムゾンは復活するクリムゾンのやろうとしていることにとっては邪魔になるという ような趣旨のコメントにもあるように、全く違うことをやろうとしたのだけれども、クリム ゾンの名前を出したがためにファンの間で混乱してしまったのだと思う) さてアルバムについてですが、私にとっての「King Crimsonの名盤の1つ」のような存在です。 1曲目の「Red」を聴いたとたん、このバンドがもう私たちの知らない別の次元へ行ってしまった ように感じました。混沌とした本当に混沌とした雰囲気の中に妙な浮遊感がある、そんな不思 議な感覚に襲われる曲です。続く「Fallen Angel」では、初期の頃を思い出させるような「絶望 的な虚脱感」漂う内容で、3曲目の「One More Red Nightmare」は、「Red」のような混沌とした 曲で、4曲目の「Providence」では即興ジャムの緊張感を如実に表された息のつけない曲に なっています。そしてラストの「Starless」はジョン ウェットンのヴォーカルが説得力を 与える切なくなるような最高のバラードであり、後半のアドリブに突入すると曲のタイトル 通り「星ひとつ無い暗闇」を見事に表現されています。 これだけ素晴らしいものを生み出していながら、なぜ解散しなければならなかったのか、私 にはよく分かりません。「第5期」がスタートしてから次々と名作を送り出してきたのだから、 恐らくこの後にも活動を続けていれば間違いなくさらに素晴らしいものを送り出してくれてい たと思うのは私だけでしょうか?とても残念でなりません。 |
|||
| The Nightwatch(Live at Amsterdam Concertgebouw November 23rd 1973) | ||||
|
1973年にアムステルダムで行われたライヴを収録したもので、伝説のライブアルバムとの呼び声も
高いアルバムです。どうしてかと言うと、「Starless and
Bible Black」に収められている曲のほとんどが、このライヴで演奏されたものをそのまま使って
いるからです。「Starless and Bible Black」だけを聴くと、ライヴ音源だとは気づかないでしょう。
それだけ、曲と演奏の完成度が高かったということです。当然ながら、このライヴアルバムと「Starless
and Bible Black」を聞き比べても全く同じものであることが分かるでしょう。
このライヴアルバムでは「Easy Money」がとてもライヴ映えしています。スタジオ版では、どことななく 「カッチリ」した感じがあり、ダイナミックな感じに欠けていたように感じましたが、ライヴではその 「カッチリ」感が抜け、いい意味でのラフさが加わっています。単純に「カッコイイ」です。全体的に そうなのですが、ヴォーカルナンバーがすべてスタジオ版に比べて格段に光を放っている感じがしました。 ただ1曲「21st Century Schizoid Man」だけは、ジョン ウェットンの声ではしっくりきませんでした。 総評として非常に完成度の高いライヴアルバムで、数あるライヴアルバムの中でも「名盤」と呼ぶに ふさわしいライヴアルバムだと思います。 |
|||